お知らせ
サービス案内
株式会社グリスタ・IDENSILに関する最新情報をお知らせいたします。
味覚の感じ方を左右させる3つの要素とは?
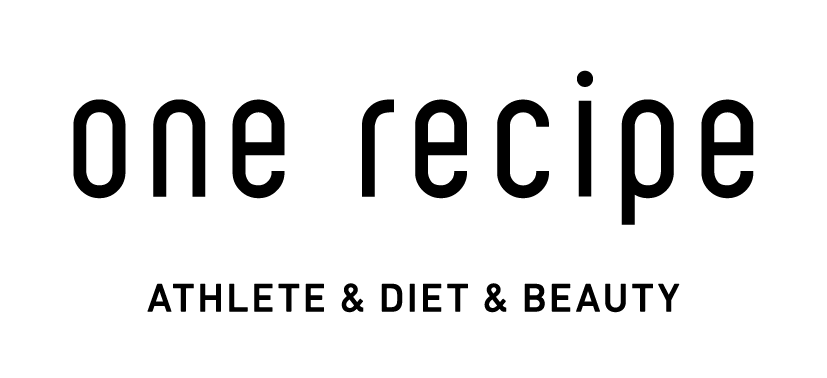
こんにちは。遺伝子分析に基づくカウンセリングサービス“ワンレシピ”事務局です。
無形文化遺産にも指定された日本が誇る“和食”ですが、和食には2つの弱点があります。
① 塩分過多
② カルシウム不足
今回は和食の弱点①塩分過多の対策についてお話ししていきます。
遺伝子分析の項目にも、塩分に対して敏感度をチェックする項目がありますが、塩分に関するリスクがある方は一層気を付けることに加え、リスクがなくても油断せず、日本人であることは食塩を容易に摂りやすい食環境にいる、ということを念頭に食生活を送るとよいでしょう。
平成29年の国民健康・栄養調査の結果を見ても、この10年で食塩摂取量は減少しているものの、それでもまだ目標量に比べて1日当たり2g以上上回っている状況です。
今回は減塩のための食材云々ではなく、味覚の感じ方の違いについて理解していただけるよう、味覚の特徴(傾向)についてお話しさせていただきます。

味覚の感じ方を左右させる3つの要素
① 温度
食べ物の温度によって味の感じ方は大きく変わります。
塩味は冷たい温度ほど強く感じやすく、温かいと塩味は感じづらいという特徴があり ます。もし冷めた状態で食べられる料理であれば、温度を少し下げてから味付けをしてみるのもよいでしょう。またいちいち冷ましたり、温めたりしてられない時は、塩味の特徴を頭に置いた上で調味をしてみましょう。
② 空腹
お腹が減っている時には、味に敏感になる傾向があるようです。お腹が減っている時は「減塩のチャンス」と考え、いつもよりさっぱりしたメニューを選んでも十分満足感は得られるかもしれません。また満腹状態の時は、逆に味に鈍感になるため濃い味を好む傾向があるようです。やはり満腹のときには余計なものは食べず、適度な空腹が減塩にも、健康にも有効なようです。
③ 時間
朝と夜で比較すると、口の中の唾液の分泌が鈍っている朝の方が、味を感じにくい傾向があるようです。口の中が渇いていると味の感受性が低くなるので、できれば起床後、コップ1杯の水を飲んだり、家族と会話をして口の中を潤してから食事をしてみるのがよいでしょう。
また生活リズムも味覚の感じ方に変化をもたらす、という研究結果もあるようです。
朝型・夜型で味覚の感じ方を比較してみると、夜型の方は朝に甘味の感じ方が鈍く(より甘さを欲するということ)夜になるとだんだん戻ってくるという研究結果があります。早起きは三文の徳と言いますが、生活リズムが味覚まで影響を及ぼすとは驚きですね。
味覚のメカニズムを理解すれば、多少たりとも減塩対策に役立てそうですね。

