お知らせ
サービス案内
株式会社グリスタ・IDENSILに関する最新情報をお知らせいたします。
糖尿病ってどんな病気なの?〜インスリンの働き〜
こんにちは。管理栄養士の中岡浩子です。
前回のコラムでは血糖が高い状態を放っておくと糖尿病を発症してしまうことや、糖尿病の種類と特徴についてのお話をしました。
>>>「糖尿病ってどんな病気なの?〜インスリンとの関係 〜」
今回は取り込まれた糖をエネルギーとして使うために必要なホルモン「インスリン」が体内でどのような働きをしているのかを詳しくお話ししたいと思います。
インスリンの働き
食事から取り込まれた栄養素の一部は糖となって腸から吸収され、血液の流れに乗ってからだ中の細胞に運ばれます。
運ばれた糖が細胞の中に取り込まれるのを手助けしてくれるのがインスリンで、たどりついた細胞の入り口を開けてくれるカギのような役割をしています。
そして筋肉や臓器などの細胞に取り込まれた糖は、活動のエネルギー源となります。
インスリンが正常に作用していれば糖はスムーズに細胞内に取り込まれ、血液中に糖があふれることはなく血糖値は一定の範囲に保たれますが、何らかの原因でインスリンがうまく働かないと、糖を取り込めずに血液中にあふれてしまいます。
インスリンがうまく働かない2つの原因と遺伝子の関係
2型糖尿病の原因であるインスリンが十分に働かない状態は2つに分けられます。
- インスリンの量が少ないことにより糖の取り込みがうまくいかない
- インスリンは十分に出ていてもその効果を発揮できないために糖の取り込みがうまくいかない
この2つの状態について、IDENSILで調べることができる遺伝子が関係しています。
状態別に詳しく見てみましょう。
インスリンの量が少ないことにより糖の取り込みがうまくいかない
IDENSILでは血糖レベルの項目の中で
- インスリン生成に関する遺伝子:CDKAL1
のリスク判定を知ることができます。
この遺伝子はアジア人特有の肥満遺伝子とも言われています。
CDKAL1にリスクがあるとインスリンの機能が低下し、血糖値が上昇しやすい傾向があります。
インスリンは十分に出ていてもその効果を発揮できないために糖の取り込みがうまくいかない
IDENSILでは血糖レベルの項目の中で
- インスリンの抵抗性に関する遺伝子:Adiponectin
のリスク判定を知ることができます。
Adiponectinは脂肪細胞から分泌されるホルモンで、インスリンの抵抗性を改善する働きをするので「やせホルモン」とか「長寿ホルモン」などとも言われています。
ここでは分泌されたインスリンをうまく使える体質かどうかが分かり、リスクがあるとインスリンの効きが悪く、上がった血糖値を下げにくい体質だと考えられます。
脂肪細胞が小さいほうがよく分泌されるので、肥満になると分泌されにくくなります。
じゃがいもやとうもろこし、ピーマンやトマト、りんごやぶどうに含まれる「オスモチン」という機能性成分にも同様の作用があると言われています。
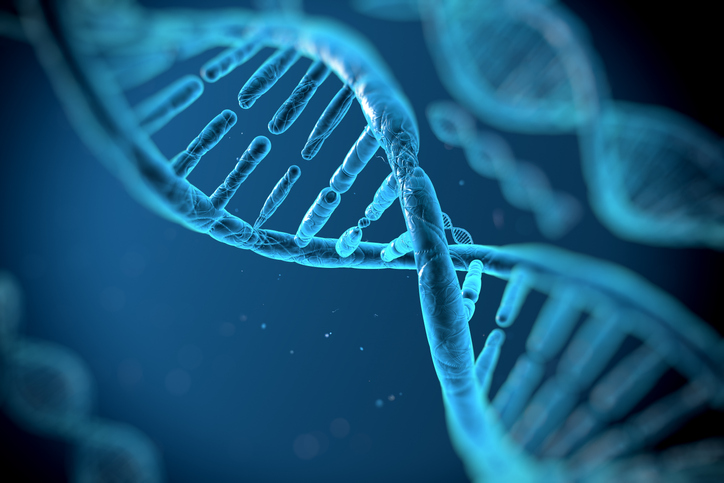
糖尿病という病気そのものが遺伝するわけではない
家族に糖尿病患者がいても誰もが発症するわけではありません。
糖尿病になりやすい体質は遺伝すると言われていますが、だからこそ食事や運動習慣の見直しをして適正体重の維持に努め、定期健診で早期に発見することも大切です。
反対に体質的に心配がなくても、不規則な生活習慣や食生活の乱れにより、発症のリスクは高くなります。
自分の持っている体質を知ることで意識を変え、病気の予防のためにできることが見えてきますね。

