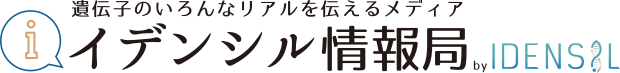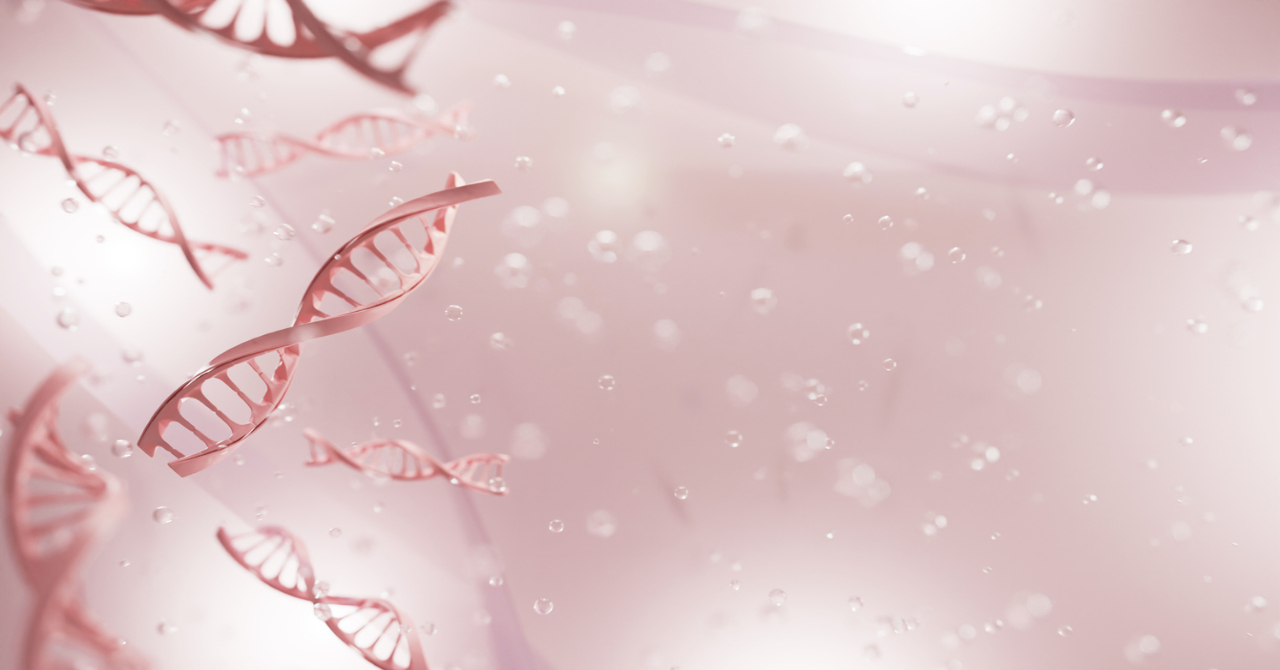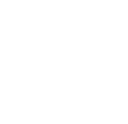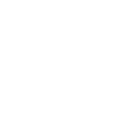#51 骨密度は生まれつき? 後天的? 遺伝子×ライフスタイルで考えるヘルスケア
皆さんこんにちは。
今回は「遺伝子検査×骨密度」をテーマにお伝えします。
少し過ぎてしまいましたが、5月23日は「骨密度ケアの日」。
骨の健康意識を高めるために制定されたこの記念日は、骨の重要性や骨密度について再認識するための良い機会です。
骨を丈夫にするためには、「カルシウムを摂る」といった対策がよく知られていますが、実はそれだけではありません。
今回は、骨密度と遺伝子の関係について、最新の考え方を交えながら、ヘルスケアの新しい視点をご紹介します。
骨密度とは? 健康寿命を支える“見えない資産”
骨密度とは、骨に含まれるカルシウムなどのミネラルの量を表す指標で、骨の丈夫さや強さと深く関係していて、一般的に20代をピークに少しずつ減少していくといわれています。
骨密度が低下すると、日常の動作や軽い衝撃でも骨に負担がかかりやすくなり、骨折に繋がるリスクがあるとされており、普段から予防への意識と行動が大切です。
こうした背景から、骨密度は“見えない資産”とも呼ばれ、若いうちからケアすることで将来の健康維持につながると考えられています。
日々の食事や運動といった基本的な生活習慣の積み重ねに加えて、体質や生活環境の違いをふまえた個別のアプローチがますます重要視されています。
骨の健康を保つために、何が必要?
では、骨の健康を保つためには、何が必要なのでしょうか。
- 栄養:カルシウムに加え、ビタミンDやビタミンKも骨の形成に欠かせない栄養素です。これらの栄養素がしっかり摂れる食事を心がけることが基本です。また、ビタミンDは日光を浴びることにより体内で生成されます。紫外線が強い時間帯を避け、日光浴をすることもオススメです。
- 運動:骨に刺激を与える運動は、骨形成を促進するといわれています。運動の専門家の指示を仰ぎ、ウォーキングや軽いジャンプなど、日常に取り入れやすいものから始めるのがオススメです。
その他、骨の健康には生活習慣やホルモンバランスなども関わってきます。
喫煙や過度の飲酒なども骨の健康に影響すると言われていますので、日頃からの規則正しい生活を心がけましょう。
遺伝子から読み解く、“骨質傾向”というヒント
近年の研究により、骨に関係する遺伝的傾向と遺伝子との関連が少しずつ明らかになってきました。
たとえば、ビタミンDの働きやカルシウム吸収に関係する遺伝的な違い、骨代謝に関わるホルモン受容体の個体差などがそれにあたります。
もちろん、遺伝子検査で「骨密度が高い・低い」といった診断ができるわけではありません。ですが、自分の生まれ持った遺伝的傾向を知ることで、どこに気をつけた方が良いかのヒントになります。
自分の体質に合ったヘルスケアを選ぶことで、より納得感のある健康づくりが可能になりますね。
今日のIDENSIL情報局は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
株式会社グリスタは個別化ヘルスケアに特化した遺伝子分析サービス「IDENSIL」の開発メーカーです。
お問い合わせはお気軽にどうぞ!
IDENSIL管理栄養士
IDENSIL(株式会社グリスタ)に所属している管理栄養士です。 遺伝子活用と栄養に関する情報をお伝えしていきます。 ※IDENSILは、健康な方を対象に遺伝的傾向を把握するためのヘルスケアツールであり、医療的な診断・治療を目的とするものではありません。本コラムでも医療用の遺伝子検査ではなく、ヘルスケア分野での利活用に限定して紹介しています。